今回は受験スケジュールの立て方について、お話したいと思います
とにかく手を動かし、前に進めることも大事ですが、最初に受験の全体スケジュールを設計してから動くことで効率的に合格に進めると思います
スケジュール策定で迷われている方、受験のスケジュール感を掴みたい方の参考になれば幸いです
1.合格の期日目標を定める

まず「いつまでに合格したい/合格しなければならない」のかという期日目標を定めましょう
予備校などで言われる一般的な目安は、「1年半で合格」です
もちろん、勉強開始前の前提知識、経験スキル/領域、担当業務、学習環境によって、1年半より短くもなるし、長くもなりますが、1つの目安に考えるのはよいと思います
以下では、1年半(18ヶ月)での合格を目標としたベースで話を進めていきますが、個人の目標期日によって、置き換えてみてください
2.1科目当たりの工数(月数)を概算
↓
各科目の(平均)準備期間算出:18ヶ月÷4科目=4.5ヶ月/科目
※実際には、各科目の勉強前or並行して受験に必要な単位の取得や必要手続きがあります
個人的な感覚としては、1科目当たり3.5ヶ月+αが準備期間のイメージです
勿論、全て一発合格を目指すべきですが、うまく進まないケースを想定しておくことも気持ちにゆとりを持つ上で重要で、3.5ヶ月で準備して、仮に失敗しても、1ヶ月でリベンジできれば、巡航速度です
※受験後、Score release→再受験手続き・受験準備→再受験で最低でも1か月は見ておいた方がよいです
また、科目毎に得意不得意もあろうかと思います
仕事で関りのある分野については、学習がスムーズに進むものもあれば、逆に全く関わりのない分野であれば、学習に時間がかかりやすくなります
なので、平均して1科目当たり3.5ヶ月という準備期間を軸に、自分の得手不得手を踏まえて準備期間を伸縮させるとよいかと思います
この試験の良いところは自ら受験日を決められることなので、準備が間に合わなければ、無理に受験する必要はありません
(但し、自ら受験日を決められることによって、受験を先延ばしにして、いつまでも前に進められなくなることには注意してください) 以前は四半期(Testing window)毎に1科目1回の受験しかできませんでしたので、3ヶ月毎に1科目受験できるように準備したい・・・という頭が私にはありましたが、実際に3ヶ月で1科目の受験準備をしようとすると、かなりタイトでした・・・
※2020年7月より制度が変わり、通年受験できることになりました
https://www.abitus.co.jp/information/uscpa/470.html
受験順については、以下の記事もご参照下さい
 【USCPA】科目の受験順おすすめ(FARが最初にして最大の難関!?)
【USCPA】科目の受験順おすすめ(FARが最初にして最大の難関!?)
3.受験までの準備

いつまでに何をどの程度進めておくと良いか、仕上げておくと良いかを考えましょう
3.1 勉強の対象(使用教材)
まず、「何を」の部分です。自分が受験までにこなさなければいけない対象を確認にしましょう
私が受験準備で使ったものは以下のものです例えば、基礎固めとして、1.5ヶ月で講義を一通り聞き、MC問題を1-2周したい場合、いつまでにどこまで進める必要があるか計画を立てます
・TB追加問題集
・AICPA Sample Test
・AICPA Released Questions
・アビタス模試
正直これだけこなすだけでも精一杯で、他の問題集、洋書に手を出す余裕はありませんでした
際にアビタスも言っていますし、多くのアビタス生もこれだけで十分合格を達成していますので、他の教材に手を出さなくても大丈夫だと思います
アビタスについてはこちらの記事もご参照下さい
 【USCPA】予備校選びに時間はかけるな!迷ったらアビタスおすすめ!
【USCPA】予備校選びに時間はかけるな!迷ったらアビタスおすすめ!
3.2 受験までの3つの段階
次に、受験までの準備を三段階に分け、それぞれに要する時間目安の時間をざっくり決めます
2.応用: MC問題(応用問題)、TBS問題→1ヶ月
3.仕上げ:AICPA Sample Test、AICPA Released Questions、模試→1ヶ月
正直、テキストを一周回すだけでも結構な労力が必要です
忘れることを前提に、高速回転させることが重要と思います
ここでも継続の力が必要で、勉強して時間が空くと、本当にザルのように忘れていきますので、毎日少しでも時間を確保し、前に進めたり、復習したりすることが大事です
近道はないことを実感しましたし、とにかく自分で前に進めないことには合格が近づかないのだと思い、自分を鼓舞していました
3.3 月/週/日ごとのスケジュールに落とし込む
私はExcelや紙に日付と曜日を縦に並べて、具体的に日付と勉強予定の章(アビタスの教材だとChapter)を紐づけていきました
例えば、基礎固めとして、1.5ヶ月で講義を一通り聞き、MC問題を1-2周したい場合、いつまでにどこまで進める必要があるか計画を立てます
この分配を書き出すだけでも、結構なペースで回していかないといけないんだな、と分かると思います
スケジュールを立てる時は、完璧なスケジュールを立てがちですが、現実には仕事が忙しくなったり、今は少ないと思いますが、急な接待や飲み会が入ってしまったり、体調が優れなかったり、様々な予期せぬ事態が起こります
なので、スケジュールには余裕を持つこと、遅れが出た際に挽回ができるように調整日を設けることも大事です
平日、全く勉強できずに週末に挽回、というのは現実的にはかなり厳しく、そうならないためにも仕事のある日でも、隙間時間を見つけて、少しでも前に進めることが大事です
3.4 習熟度の目安
USCPAの勉強では、「勉強時間」が語られることが多いですが、勉強時間=習熟度ではありません
習熟度の目安は
- 論点理解:問題を見た時に問われている論点が分かるか
- 正答率:MC問題であれば90%くらいの正答率か
- 解答時間:1問1分半(90秒)くらいで解けるか
を見ていくとよいです
解答時間は仕上げ期間に本番を意識して90秒くらいで解けるような状態にしていけばよいので、特に基礎固めの時期は意識しなくても大丈夫です
論点が理解できること、多少時間が掛かっても自分で解けるか試してみましょう
逆に、論点が分からなかったり、解答への道筋が掴めない場合は、すぐに解答を見て、論点や解き方を確認してしまいしょう
4.まとめ
いかがだったでしょうか
スケジュールは実際に自分で手を動かして、具体的に書き出し、実感することが大事です
また、実際に走り出した後、日々の進捗状況に応じて修正を繰り返していくことになります
日ごとに落とし込むと言いましたが、最初は月ごと、週ごとにどこまで進めるかといった、ざっくりとしたスケジュール表でもよいので、是非一度作ってみてください!
一日一日の努力が、合格に近づきます!
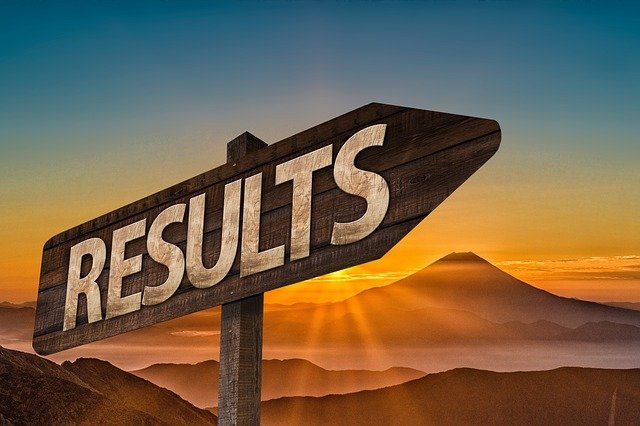
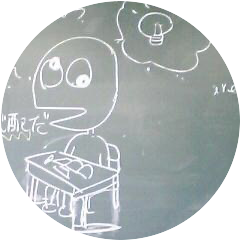 アンポンタンポカンくんの108ブログ
アンポンタンポカンくんの108ブログ 

